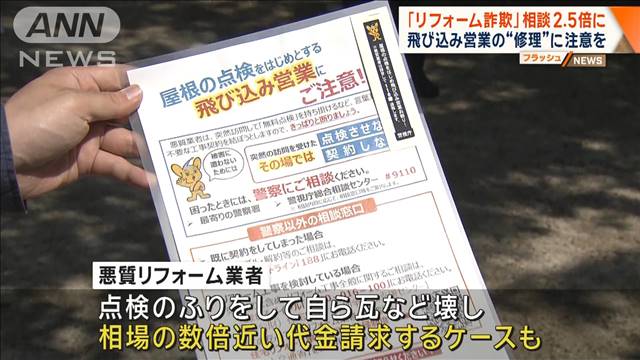裁判官はどんな状況でも正しい判断を下せるのか-。東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件の公判で、被告側が担当する3人の裁判官を審理から外すよう申し立てた。理由は、社会心理学の分野で「偏見」を示す「認知バイアス」の影響を裁判官が受けた恐れがある、というもの。申し立ては却下されたが、最新の研究では、公正を旨とする裁判官といえども偏見から逃れられないとする報告もあるといい、法曹界で注目を集め始めている。
「真っ白で向き合えず」
東京地裁に対し今年2月、裁判官を審理から外す「忌避申立」を行ったのは、大会スポンサー企業から賄賂を受け取ったとして受託収賄罪で起訴され公判中の深見和政被告(74)の主任弁護人を務める、高野隆弁護士らだ。
一連の汚職事件では、5ルートで15人が起訴された。深見被告の公判を担当している3人の裁判官は、別の贈賄側や収賄側の公判を担当し、いずれも有罪判決を下している。
高野弁護士は、こうした経緯のある裁判官が深見被告の事件に「真っ白な状態で向き合うことが不可能だ」などと主張。補強材料として社会心理学用語である「認知バイアス」に言及した。
だが、地裁は「訴訟を遅延する目的のみでなされた」として申し立てを棄却。弁護側は東京高裁に抗告、最高裁に特別抗告したが、いずれも退けられた。
海外で進む研究
偏見や先入観、思い込みなどといった意味を持つバイアス。裁判官や、有罪か無罪かを判断する陪審員の候補となる市民に裁判で生じうる「認知バイアス」についての研究は、海外で進んでいる。
米国で1994年に発表された、現役裁判官と陪審員候補の市民計約200人を対象にした実験では、自宅の庭で燃料容器を使って落ち葉を燃やそうとしてやけどを負った原告がメーカーを訴えた訴訟を題材に、どんな判断を下すかを調査。
裁判官らの一部に「実は、容器はリコール対象だった」という原告に有利な情報を見せ、さらにその一部には「その情報は判断材料にしてはいけない」との縛りを設けた上で、判断の揺らぎを調べた。
結果は、原告に有利な情報が示されなかった裁判官31人は、全員が会社側の責任を否定。一方、原告に有利な情報をみせられた裁判官のうち、判断材料にしても「よい」とされた裁判官28人中7人(25%)が原告の訴えを認めた。判断材料にすることを禁じられた裁判官でも、ほぼ同様の割合の29人中7人(24%)が原告の訴えを認めた。
プロの裁判官であっても、一度目にした情報を「判断材料にしてはいけない」と分かっていても、実際に判断を下す際にはその情報を排除しきれない可能性を示唆する結果となった。
より公正な裁判に
認知バイアスに詳しい関西大の藤田政博教授(社会心理学)は「一度見た証拠を見なかったことにして判断するのは難しい。公平公正な裁判をする訓練を受けている裁判官であっても、認知バイアスに陥る可能性はある」と分析する。
藤田教授によると、国内での認知バイアスの事例研究は道半ばだが、米国などでの複数の研究から、裁判官が「本来は考慮すべきでない要素を排して判断を下す」ことの難しさが明らかになっているという。
藤田教授は、裁判官が認知バイアスの影響を受けていた場合でも、下された判断が間違ったものだとは限らず「直ちに裁判の正当性が失われるわけではない」とも指摘。
今後は、こうした心理学の研究成果への理解を裁判官に深めてもらうことで「より公正な裁判になるだろう」としている。(星直人)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。